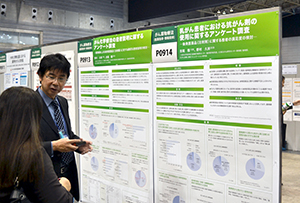
2015年11月21日(土)〜23日(月)に、パシフィコ横浜(神奈川県)にて開催された第25回日本医療薬学会年会で、2015年春にがん診療と患者コミュニケーション研究会が行ったアンケート調査について、世話人の野村久祥先生(代表、国立がん研究センター東病院)と吉尾隆先生(東邦大学)よりポスター発表がありました。
野村先生は、薬剤師を対象とした「がんのお薬の患者説明についてのアンケート」について、吉尾先生は、乳がん患者を対象とした「がんのお薬についてのアンケート」について発表しました。今回、お二人より発表内容についてメッセージをいただきましたので掲載いたします。
P0913-22-PM
がん化学療法の患者説明に関する
アンケート調査
-薬剤師による後発医薬品(注射薬)に対する適切な患者説明の検討-
P0914-23-AM
乳がん患者における抗がん剤の使用に関する
アンケート調査
-後発医薬品(注射剤)に関する患者の満足度の検討-
Message:吉尾 隆先生(東邦大学薬学部 医療薬学教育センター)
 今回の乳がん患者を対象としたアンケート調査により、患者さんは、薬剤師による抗がん薬の説明をかなり信頼しており、薬剤師からの説明を受けたいと強く希望していることがわかりました。しかし、薬剤師がそれに対応できておらず、患者さんへの抗がん薬に関する情報提供が十分でないようです。そのため、患者さんも抗がん薬による治療を受ける際に、先発医薬品と後発医薬品のどちらかを選択しようにもできない状況がうかがえます。
今回の乳がん患者を対象としたアンケート調査により、患者さんは、薬剤師による抗がん薬の説明をかなり信頼しており、薬剤師からの説明を受けたいと強く希望していることがわかりました。しかし、薬剤師がそれに対応できておらず、患者さんへの抗がん薬に関する情報提供が十分でないようです。そのため、患者さんも抗がん薬による治療を受ける際に、先発医薬品と後発医薬品のどちらかを選択しようにもできない状況がうかがえます。抗がん薬後発医薬品に関しては、経済的な面だけでなく、効果・副作用についても先発医薬品との違いなどを説明しないと、患者さんは治療薬を選択するための情報が不足してしまいます。アンケート回答者の半数強が後発医薬品の使用を希望していないことも踏まえ、抗がん薬後発医薬品の使用の際には効果・副作用まで十分な説明を行っていかなければならないというのが、今回のアンケート調査からみえてきたことだと思います。
当発表ポスターを閲覧された方には、薬剤師の役割として抗がん薬後発医薬品の使用の際の積極的な患者説明について、どう考えられておられるのか、当研究会HPへご意見・ご相談をお寄せいただければと思います。
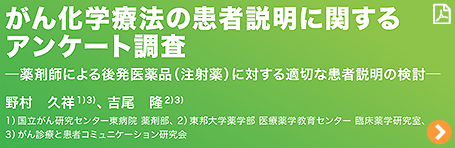
※こちらの記事の閲覧には会員登録が必要です。
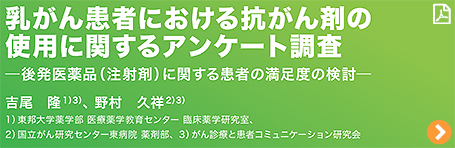
※こちらの記事の閲覧には会員登録が必要です。
先生方からのご意見・ご感想
最近では、後発医薬品が当たり前のように使われることが多く、それは抗がん剤についても同様である。今回の乳がん患者および薬剤師に対するアンケート調査により、患者としては後発医薬品への変更をそれほど希望していないにもかかわらず、われわれ薬剤師は先発医薬品との違いや特徴、値段などを含め、十分な説明ができていないことが明らかとなった。実際には国や病院の方針として後発医薬品に変更されていることがほとんどではあるが、それでもわれわれ薬剤師は患者が納得して「薬物」治療を受けられるよう、受け身ではなくわれわれ自身の方から積極的に情報提供することが必要だと考えられる。
(輪湖哲也先生・日本医科大学付属病院薬剤部)
薬剤師が行う注射抗がん剤の治療の説明は患者から非常に信頼されている反面、多くの患者が説明を望んでいる後発医薬品の使用に関して、薬剤師は積極的に説明を行っていない現状も浮き彫りとなった。患者側アンケートでは、その大半が注射抗がん剤の後発医薬品への変更を希望していないなか、病院においては政策や経営上の理由により今後も積極的に後発医薬品の使用が推進されていくのは明らかであり、患者に不安や誤解を与えないよう薬剤師が後発医薬品ついてより積極的な説明を行うことが望まれる。
(岩井 大先生・東京西徳洲会病院薬剤部)
Message:野村 久祥先生(国立がん研究センター東病院 薬剤部)
また、病院で採用が決まった後発医薬品に対して薬剤師が介入できる部分は少ないとはいえ、薬剤師からの説明等は十分ではないことがわかりました。今後、薬剤師はがん治療における後発医薬品の使用に関してもっと積極的に介入・指導していくべきだと思います。
最後に、がん診療において、病院薬剤師とは担う部分は異なりますが、保険薬局薬剤師にも抗がん薬使用における患者さんへの介入や指導をもっと積極的に行っていただきたいと思います。その際、疑問や困ったことが生じると思いますが、それらについて当研究会HPよりご意見・ご相談をお寄せいただければ幸いです。私たちもいっしょに検討し、薬剤師として患者さんの満足度、QOLの向上に寄与できるような仕事を模索していきたいと思います。